自分たちの人生を一歩上のレベルに
持ち上げてみませんか?

HP掲載の狙い目とキーポイント
ヒトはだれでも、この世に生を受けてから一生涯を終えるまで、その時々の情勢に従って、自分の意思を明確にしつつ生き続けなければなりません。
人生は、老若男女、国籍、人種、宗教、文化、信条、教養などに捕らわれることなく、公平かつ対等な営みを享受できるように努力・精進することが大切です。そして何よりも健康で幸せな人生を送られることが究極の目的になると考えています。
そうはいっても、毎日の暮らしの中で、悩みや不都合なことなどが多く発生し、解決しにくい問題や心痛などが間断なく襲い掛かってくることがあります。
そんなときのために、問題解決の一助になればと考え、このホームページ(以下、HPと略します)を立ちあげましたので、参考にして頂けると幸甚です。
ただし、このHPはあくまでも個人的な意図で掲載しますので、問い合わせや 意見・提案などには一切お答えできませんのでご了承ください。
さらに、このHPはこま武蔵台の皆さんが参考程度に閲覧して頂くように編集しておりますので、ご理解頂きますようお願いします。
このホームページに記載された内容は、筆者の自由意思いいddsで作成したもので、その著作権(権限)はすべて筆者にあります。従いまして、閲覧者が何らかの手段で他に情報提供しても良いですが、その場合は自己責任の下で行ってください。筆者は一切の責任を持ちませんので、ご理解とご協力をお願いします。
また、記載された情報は、令和8年(2026年)3月末までを有効期限とし、それ以降のメンテナンスは行いませんのでご承知おきください。

豊かで楽しい毎日を送るヒント
豊かな暮らしを!
「豊かさ」には、経済活動の成果に加えて、文化の創造・享受、充実した日常生活の営み、旬の食べものやおいしい水に恵まれたくらし、環境への負荷が少なく循環を基調とし自然・生物と共に生きる生活、美しい風土、静謐(せいひつ=静かで落ち着いていること
)な生活環境、慈愛や奉仕といった社会活動の成果が含まれます。豊かな暮らしとは、小さな幸せを感じられる暮らし、自由に選択できる暮らし、体や心が健康でいられる暮らしを指します。
高みを目指して!
ライフハックは、生活や仕事の日常的な課題を解決するための知恵やテクニックを指します。効率的に仕事をこなす方法やストレスを軽減する方法、便利に生活する方法など、実用的なアイデアや方法を総称します。つまり、このことはとりもなおさず人生の設計を自ら行い、そのシナリオに従って向上心を保ちながらより良い暮らしを目指すことを意味します。だからヒトは常に自分の人生を見つめ、時には高みを目指して突き進んでいくことが求められるのです。




幸せの未来像
「幸せとは何ぞや?」と問われると答えを見つけるのがとても難しいように考えますが、いかがでしょうか?
「幸せ」とは、一般的には「その人にとって不満がなく、望ましい状態」のことを指します。また、心理学では「well-being(ウェルビーイング)」と呼ばれ、持続的により良い状態になることとして考えられています。さらに、「幸せ」は運やめぐりあわせがよいこと、個人にとって望ましく満足なことを意味し、心が満ち足りている状態とも言われています。哲学的には、個人の欲望と社会の規範のバランスを取り、調和のとれた生活を送ることが幸せとされています。
私たちは、この世に生を預かって以来、将来に希望を持ち歩み続けていますが、すべてが個々の人生プランの通り進行するわけではありません。むしろ解決が困難な局面に遭遇したり、悩みの多い課題に直面して、ハラハラドキドキの人生を余儀なくされることがあります。
そんな中で、私たちはどんな困難にでも全知全能を傾けてそれらの問題に立ち向かい、切り開きながら自分の人生を全うするしかないのです。
本当の幸せって、日常生活の中から必然的に生まれ出るものです。
無理をしたり、焦ったりせずに急がずに自分のペースを守りつつ、豊かで幸せな日々を積み上げて行くことから始めましょう!?

幸せの定義
幸福とは何か?
厳密な定義は難しいですが、幸せは心の状態であり、簡単にいえば「安心や満足」といえるでしょう。「式」で表すと次のように簡略化して表現できます。
幸せ = 安心 X 満足
「コトバンク」によれば、「幸福感は,1998年にセリグマンSeligman,M.E.P.によって提唱されたポジティブ心理学positive psychologyの主要なテーマの一つである。ポジティブ心理学は,21世紀の心理学の研究と実践では,ポジティブな感情や認知,組織などを系統的かつ科学的に取り扱うことを重視するべきだとする学問的運動である。」
ここで挙げた「幸せ」は、個人的なもであり人それぞれが違う値を持ちます。 例えば、幸せの度合いを最大で”1”(100%) として、 「安心」が最大で”1” で、「満足」も最大で ”1”とすればよいのです。
ここでイメージすべき「幸せ」とは、どのようなものでしょうか。具体的なイメージは、人によって異なりますが、
- 幸せな家庭を築き
- 裕福な生活を送り
- 仕事でも一目おかれる立場になり
- 多くの人から感謝され
- 好きな時間に好きなことができる
と言えなくもないでしょう。更に上述した幸せの定義は。家族 金 財 地位 名誉 健康状態 なども含めることができます。
このような定義に照らし合わせて「幸せを感じる人物像」を鑑みると、自分の幸せ感を測定・観察できます。例えば、現時点で"0.8"という測定値を得たなら、時間の経過とともにその値がどのように変化するのかを観察すればよいのです。
コミュニティの創造
コミュニティを創造するためには、以下のことが必要です。
- 仲間を集める
- ミニ集会を開く
- 仲間との連絡手段をつくる
- 自分のコミュニティのHPをつくって広める(本HPの狙い目)
- 街に住む人を知り、街にある施設を知ること(困ったときに活用)
- バランスの良いコミュニティ形成をする(10軒程度の小グループに区分けして、それら全体を自治会が管理・運営する)
- 街、地域というコミュニティをバランスの良いつながりで人々の健康と安心につながるコミュニティにする 端的に言えば、「向こう三軒両隣」(最小単位:6軒) の構築と円滑な運用がポイントで、これが新しいコミュニティとなります。

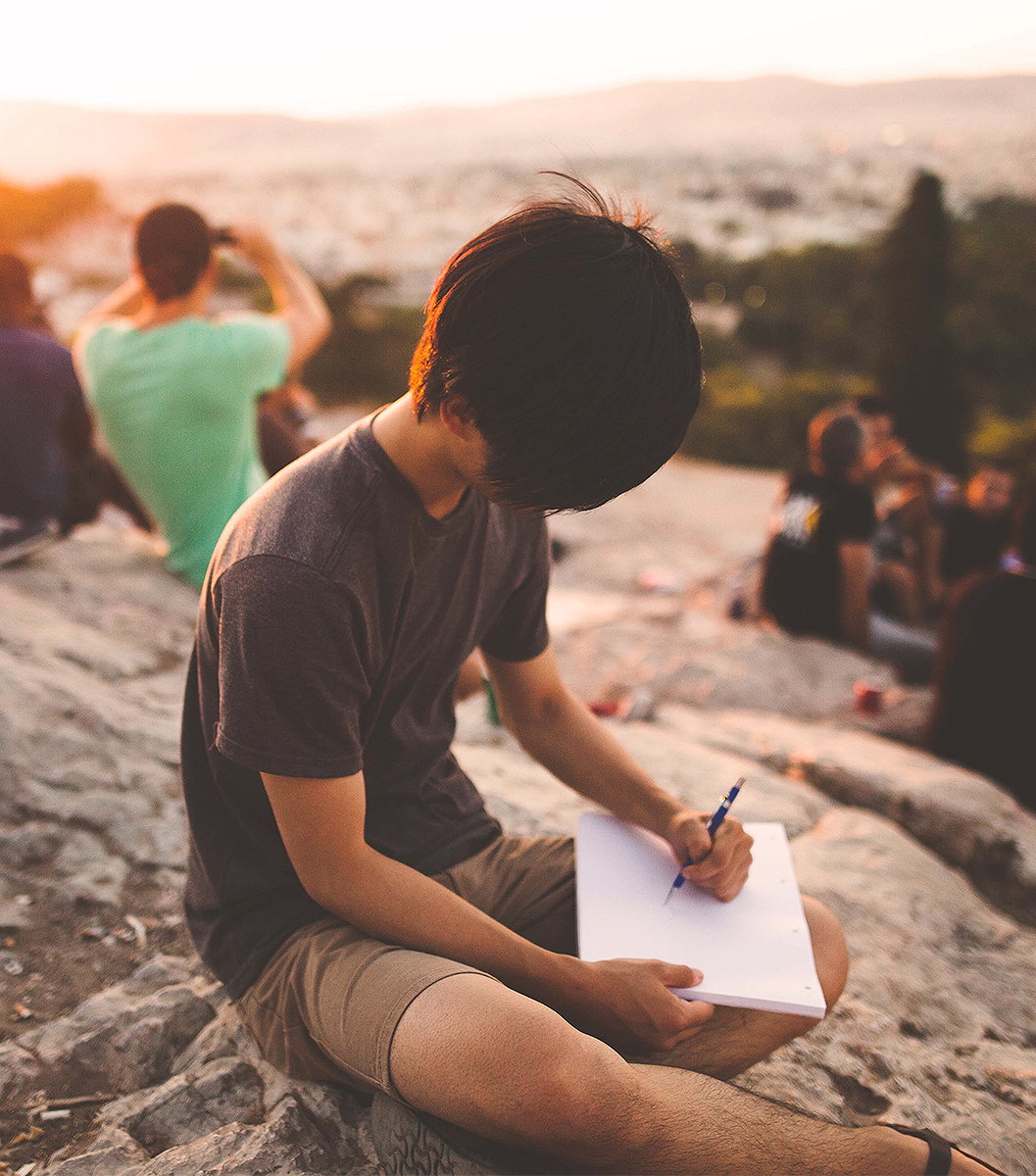
コミュニケーションの多様化と実践的運用
思いやりや近隣との助け合い精神の習慣化と励行の徹底化(ゆとり社会の構築)
- 犯罪から守る警備体制強化と犯罪撲滅キャンペーンの実施(子供から老人まで)
- 情報化社会の構築と積極的な活用(AI、ICT、IoT、ビッグデータなど)
- 都市間、企業間の協力体制構築と実践的運用(システム構築と強固な実行力)
- 技術・文化交流を通した連帯感の育成と協力体制の強化(交流センターの設立)

安全安心の確保
1. 安全・安心な社会の概念
安全・安心な社会を構築するためには、目指すべき安全・安心な社会のイメージを明確にすることが必要です。そこで、そもそも安全とは何か、安心とは何か、について検討しそれらの検討結果と社会を巡る諸情勢の変化を踏まえ、目指すべき安全・安心な社会を構築することが先決です。
2. 安全・安心な社会の構築
全国地域安全運動では、「子供と女性の犯罪被害防止」「特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害防止」「自転車盗、万引きの被害防止」を全国重点として、不審者情報や特殊詐欺などに関する早期通報の呼びかけと効果的な情報発信、警察や地方自治体、学校と防犯ボランティア団体などの連携強化、危険箇所の点検・改善、防犯教室の開催など、様々な活動を展開しています。
これ以外にも次の安全・安心に関する内容が対象として挙げられます。
- 地域の安全サイト
- 安全運転
- 防災
- セキュリティ対策
- 一般疾病・再生医療
- 安心介護
- 救急医療
- 資産・財産の管理

安全安心の定義
<安全とは何か>
1 安全とは
安全とは、人とその共同体への損傷、ならびに人、組織、公共の所有物に損害がないと客観的に判断されることです。ここでいう所有物には無形のものも含みます。
2 設計および運用段階の安全
社会において、様々なシステムや制度が人間の手で設計され、運用されています。これらの安全について考えた場合、安全とは、設計段階において安全性が十分に考慮されているとともに、人間が運用する際における安全が確保できている状態を指します。また、安全を侵害する意図が存在する場合は、いま述べた状態に加えて、その意図の抑止・喪失が実現できている状態でもあります。
3 事前および事後対策の実現による安全
安全を脅かす要因(以下、リスクと略す)による被害を最小限に抑えるためには、発生抑止や被害防止等の事前対策に加え、発生後の応急対応や被害軽減、復旧復興等の事後対策も含めた総合的な対策が必要とされます。したがって、リスクに対して、事前および事後対策の両方がなされている状態が安全であるといえるでしょう。
4 個人の意識が支える安全
社会システムが、利用者である個人の行動と密接に関連しているということは、社会システムの安全が何らかの方法で確保できても、安全を考慮せずに個人が行動すれば、安全な社会は容易に崩れることを意味します。 したがって、社会システム固有の安全性に加えて、利用する個人が安全に対する知識・意識を持ち、それに沿った行動をとることで初めて、安全が確保されるといえます。
5 リスクの極小化による安全
世の中で起こりうる全ての出来事を人間が想定することは不可能であり、安全が想定外の出来事により脅かされる可能性は常に残されています。そこでリスクを社会が受容可能なレベルまで極小化している状態を安全であるとしています。同時に社会とのコミュニケーションを継続的に行う努力をすることにより、情勢に応じて変動しうる社会のリスク受容レベルに対応する必要があります。
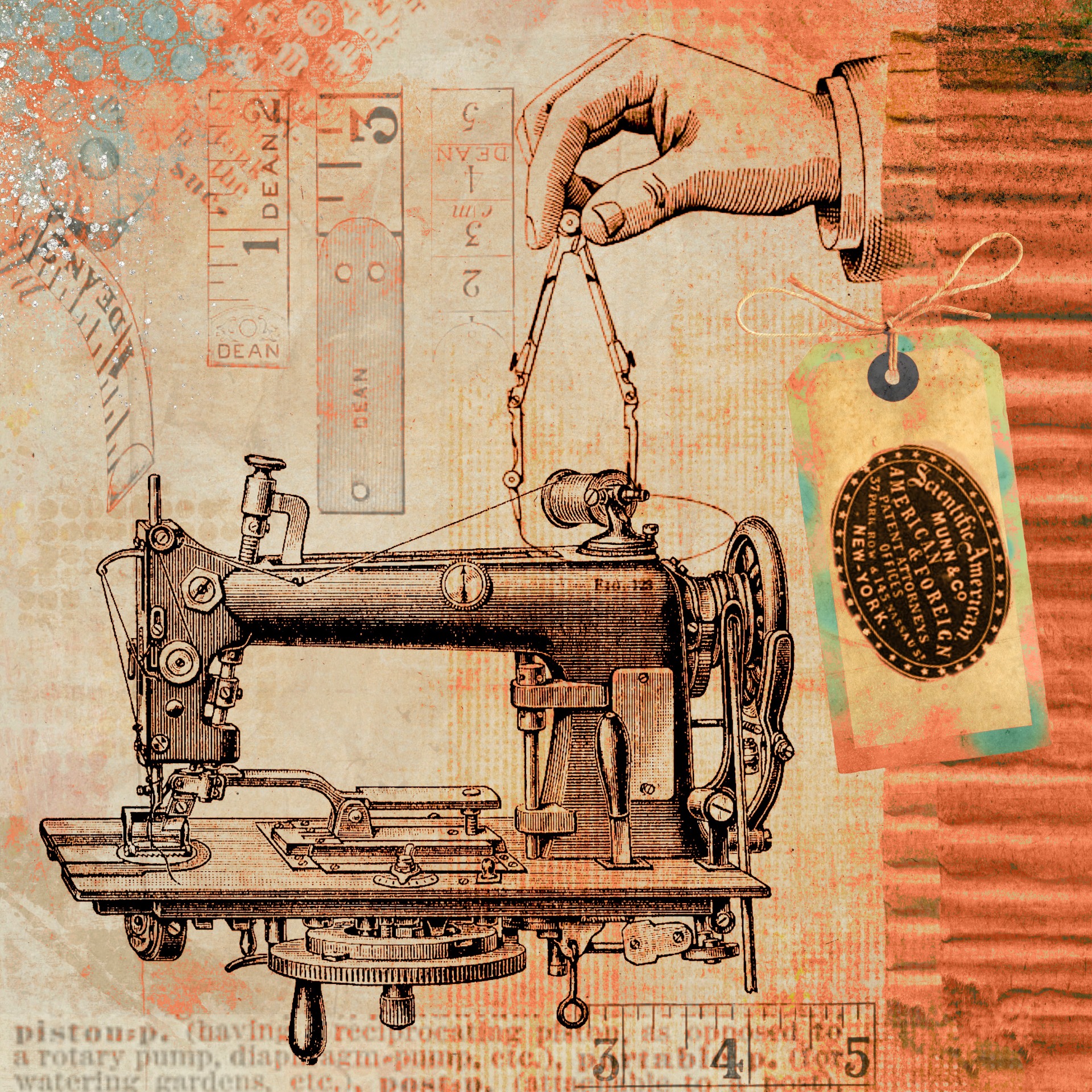
<安心とは何か>
安心とは何かについても、安全と同様に、社会との関わりを中心として検証を試みました。その結果は、次の通りです。
1 安心について
安心については、個人の主観的な判断に大きく依存するものです。当ここでは安心について、人が知識・経験を通じて予測している状況と大きく異なる状況にならないと信じていること、自分が予想していないことは起きないと信じ何かあったとしても受容できると信じていること、といった見方が挙げられます。
2 安全と信頼が導く安心
人々の安心を得るための前提として、安全の確保に関わる組織と人々の間に信頼を醸成することが何よりも必要なことです。なぜなら、互いの信頼がなければ、安全を確保し、さらにそのことをいくら伝えたとしても相手が安心することは困難だからです。従って、安心とは、安全・安心に関係する日知たちの間で、社会的に合意されるレベルの安全を確保しつつ、信頼が築かれる状態を指しています。
3 心構えを持ち合わせた安心
完全に安心した状態は逆に油断を招き、いざというときの危険性が高いと考えられています。だから、人々が完全に安心する状態ではなく、安全についてよく理解し、いざというときの心構えを忘れず、それが保たれている状態こそ、安心が実現しているといえるでしょう。

